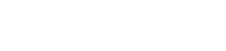生前整理のメリット&起こりやすいトラブルを知っておこう!

終活や断捨離がブームとなり、その一環で生前整理する人が増えてきました。
生前整理すれば、本人が亡くなった後の遺品整理も楽になります。
また、財産も整理するので相続のトラブルも発生しにくくなります。
一方、本人が元気な時にする生前整理は親子の価値観の違いから言い争いになることもあります。
また、財産目録などは正確に整理しないと、後の相続の際に大きなトラブルになることも。
今回は生前整理のメリットと生前整理している時に起こりやすいトラブルをまとめました。
目次
生前整理とは
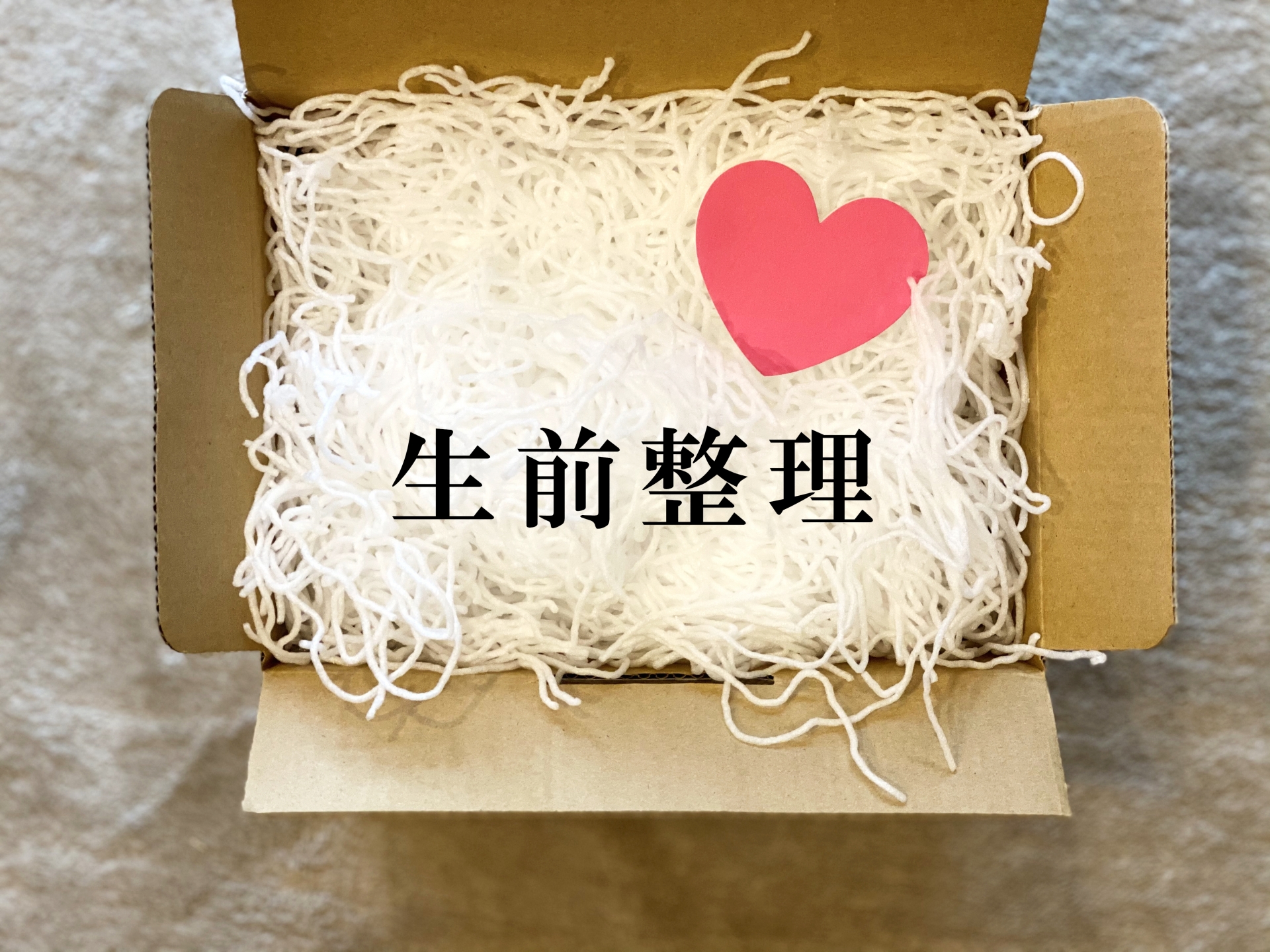
本人が亡くなってからする物の整理を「遺品整理」。
本人が生きているうちにする物の整理を「生前整理」といいます。
国勢調査によれば、ひとり暮らしをしている「単独世帯」は1,841万8000世帯。
そのうち65歳以上の単独世帯は592万8000世帯になっています(平成27年調査)。
平成22年の調査に比べると、単独世帯は9.7%増、65歳の単独世帯は23.7%と大きく増えています。
また、このような傾向は今後も続くと。そして、2035年には男性の16.3%、女性の23.4%がひとり暮らしになると推計されています。
このような背景から、残された家族に迷惑をかけたくないと「生前整理」をする人が増えています。
生前整理をはじめるタイミング
それでは生前整理をいつ頃はじめたらいいのでしょうか?この時期は決まった答えがありません。
たとえば、若い人のひとり暮らしでも、突然の死はあり得ます。その時、家族が遺品の整理に困らないかといえば、困ると思います。とくにデジタル遺品と呼ばれる情報は若い人ほど多いでしょう。
このように考えると生前整理する一番よいタイミングは、「生前整理」という言葉やメリットを知った時といえます。
しかし、「生前整理」は物の片づけが中心になるので、後回しになりがちなのも事実です。
生前整理は体力と気力を使いますので、元気なうちにはじめることがベストです。
一般的には40代から60代がよいといわれています。
この他にも人生の節目を基準にするのもよい方法です。
たとえば以下のような時期が考えられます。
・自分自身が定年退職を迎えた時期
・配偶者が亡くなった時
・自分で決めた年齢に達した時
生前整理は物の片づけだけでなく、今まで生きてきた人生を振り返る機会にもなります。
そして、これからの人生を考えるきっかけにもなります。
ぜひ、挑戦してみてください。
生前整理のメリット

生前整理するメリットは数多くあります。
大きく「自分のため」「家族のため」に分けられるでしょう。
本人にとって住みやすい環境になる
年齢を重ねていけば誰でも自然に物は増えてきますね。
生前整理すれば、不要な物を処分でき、快適な住環境で暮らせます。
また、国民生活センターによると、65歳以上の事故のうち、71.4%が住宅内で発生しているそうです。
物の整理ができれば転倒のリスクを下げられます。
転倒による骨折から、寝たきり・認知症が進んだという話はよく聞きます。
自分の意思で残す物を決められる
遺品整理の場合、本人は亡くなっているので、物の整理は遺言書などに託すしか方法がありません。
生前整理は自分の意思で残す物を決められます。
自分の意思で残す物を決めるわけなので、その後は本当に必要な物に囲まれて快適な人生を過ごせるでしょう。
また、物だけではなく、財産の管理も明確にできます。
精神的に落ち着く
「どれだけ物があるのか?」「どんな財産があるのか?」「何を残すのか?」。
これらがはっきりしていなことはありませんか?このような漠然としたことが不安につながっていることもあります。
生前整理では、物・財産・交友関係などを見直せます。
また、家の中もキレイな状態になるので。精神的に落ち着くことが多いのです。
認知症に備えられる
内閣府の推計では65歳以上の人の5人に1人が認知症になると見込んでいます。
認知症になるリスクは非常に高いのです。
認知症になってから生前整理を開始すると、本人の意向が反映できないこともあります。
そのためにも認知機能がしっかりしたうちに生前整理したいものです。
また、生前整理しておくことで、自分が認知症になった場合に備えられます。
家族にとっても、わかりやすい
突然の入院、これは誰にも予想できません。
この時、自宅の中が整理していない状態で家族が必要な物を準備できるでしょうか?健康保険証・通帳・印鑑・着替えなど。
生前整理しておけば、急な入院や介護施設へ入所することになった時、どこに物が整理されているか、わかりやすいと思います。
家族も必要な物を見つけやすく、助かることでしょう。
相続のトラブルを防ぐ
生前整理の目的のひとつに、財産を整理することがあります。
財産を整理しないで相続をした場合、相続人である家族間でトラブルになることも。
とくに簡単に分割できない不動産は問題になることが多いようです。
使っていない不動産は売却し現金化すれば、相続しやすくなります。
また、自分を介護してくれた家族に遺産を多く残したいのであれば、遺言書を作り相続させる方法もあります。
生前整理のトラブル
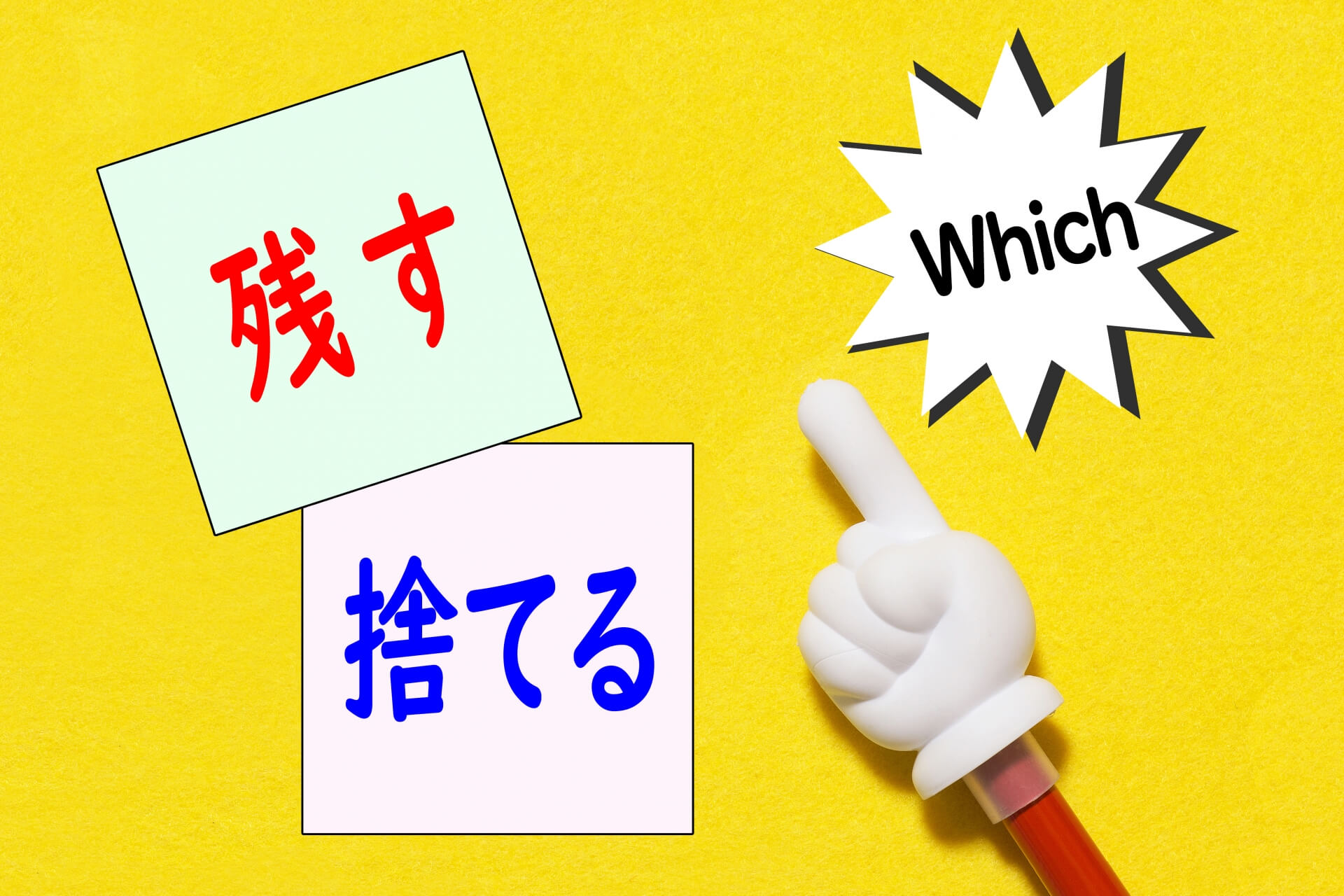
生前整理は自分ひとりでもできます。
しかし、思ったより作業が多いので、親子ですることもあります。
相続を考えると、相続人である子どもと一緒に作業することは相続のトラブルを防止する上でもよい方法です。
ここでは生前整理の現場でよくあるトラブルをまとめてみました。
処分する物で親と言い争いになる
親世代は長く生きてきた分、持ち物が思っている以上に多いでしょう。
とくに価値判断が難しいコレクションは親にしか価値がわからない物もあると思います。
物を整理していく時に子どもが不要な物と思っても、親が必要な物だと言うこともあるでしょう。
これで親子の言い争いになることもあるそうです。生前整理の主役は親なので、最終的には親が決めるといいでしょう。
ただし、先の相続のことを考えると、財産目録は作っておくべきです。
相続のトラブルを予防できます。また、最近、注目を集めている「デジタル遺品」も整理しておきましょう。
ネット上に証券口座がある場合も。
相続に関するトラブル
生前整理は物の整理だけではなく、財産の整理も必要です。
財産目録を作り、財産を明らかにする。
この際、マイナスの財産(借金)も調べておく必要があります。
マイナスの財産の存在がわからないと、相続人が相続放棄をした方がよいか判断できません。
また、不動産は現金と違って簡単に分割できません。
可能な限り現金化することをオススメします。
資産家はあらかじめ相続税対策をしています。
そのため相続のトラブルは起きにくそうです。
相続税を払わなくてもいい普通の家の方が相続に関して係争になっています。
物の処分に関するトラブル
生前整理・遺品整理では不要な物が多く発生します。
これらの中には自治体がゴミとして引き取ってくれない物があります。
自治体が定めたルールで処分することが必要です。
中には自治体のゴミ処理施設へ直接搬入する必要がある物も処分する物の中には大きく、重たい物もあるでしょう。
このような場合、自分自身の負担が大きければ、自治体が定めた業者に依頼する方法もあります。
また、家電リサイクル法によって定められた、テレビ・エアコン・冷蔵庫・洗濯機は注意が必要です。
定められたルールで処分しましょう。
専門業者とのトラブル
家庭からでた不用品を収集・運搬するためには、自治体の許可(産業廃棄物収集運搬許可)が必要です。
許可を得ていない業者に処分させた場合、不法投棄となり後日、警察から電話がかかってきたという話も。
また、不用品を買い取ってもらう場合にも古物商の許可が必要です。
国民生活センターにも遺品整理サービスでの契約トラブルが届けられているそうです。
専門業者に依頼する時は、必要な資格をもっているか十分問い合わせてみましょう。
生前整理はゆっくりと

生前整理をした方がいいかといえば、間違いなくした方がいいといえます。
とくに相続を考えると、本人にしかわからない財産の存在を明らかにできるからです。
借金があるとわかれば、相続を放棄する選択もできます。
一方、物の整理は親世代と子世代では価値観が違うため、簡単には進みません。
生前整理は親が主役なのでできるだけ親の意見を尊重しましょう。
また、整理中に思い出のアルバムが出てきた場合など、手を止めて親と思い出を共有しましょう。
それくらいの余裕で生前整理は進めるとよいと思います。
親も子も生前整理は慣れない作業で、わからないことやさまざまなトラブルに巻き込まれるかも知れません。
また、親と子が遠方で離れて暮らすことも多くなりました。
体力も気力も使う生前整理です。親子が離れて暮らしている場合、「生前整理」「遺品整理」の専門家にお願いする方法もあるでしょう。
親の生前整理を手伝うことは、最期の大きな親孝行になるかも知れません。
悔いの残らないようにやりたいですね。